季節の変わり目!春バテに要注意!
【大阪/梅田】大阪駅前の総合内科クリニック|西梅田シティクリニックがお届けする健康情報。
是非、みなさまの健康管理にお役立てください。

花粉の飛散もはじまり、まだまだ寒い日が続きますが、そろそろ春が訪れるころとなりました。
季節の変わり目は体調を崩しやすい時期とされていますが、その中でも春は多くの人が心や体に不調を感じると言われています。
そんな不調を軽減するために「春バテ」の原因や対処法について知っておきましょう。
春バテってなに?
春バテとは、就職や進学といった春特有の生活環境の変化や、激しい寒暖差などがストレスの原因となり、心や体にさまざま奈症状を引き起こすことをいいます。
また、春は四季の中で最も寒暖差が大きく、寒暖差疲労が起きやすい季節とされています。
寒暖差疲労とは
1日の気温差が大きいと、体温を調節する自律神経が過剰に働き、心身にさまざまな不調を引き起こしてしまいます。
これを寒暖差疲労といいます。
自律神経は、気温に合わせて体温を上げたり下げたりと調節しています。
しかし、寒暖差が大きいとその働きが何度も繰り返し行われます。そのため、自律神経が過剰に働き、疲労やさまざまな症状を誘発してしまいます。
寒暖差疲労の主な症状には以下があります。
- 頭痛、肩こり、腰痛
- 倦怠感
- 不眠、めまい
- 食欲不振
- 冷え、むくみ
- 下痢、便秘
- イライラ
春バテの症状
- 倦怠感
- 日中の眠気
- めまい、立ちくらみ
- イライラ
- 気分の落ち込み
- 憂鬱感
- 疲れやすい
- 食欲がない
- 朝、起きるのがつらい
気圧の変化と生活環境の変化
春バテの原因は激しい寒暖差の他に、気圧の変化や生活環境の変化があります。
①気圧の変化
春は移動性高気圧の影響で、低気圧と高気圧の入れ替わりが頻繁に起きます。
気圧が上下すると、耳の奥にある三半規管や前庭といった体のバランスを保つ気管が集まる「内耳」という部分が敏感に感知し、脳に伝達します。
それに自律神経が反応して、交感神経を刺激します。これが抑うつやめまいの悪化、血圧の上昇、心拍数の増加、慢性痛の悪化などに繋がります。
②生活環境の変化
春は進学や就職、転勤、異動、引越しなど、新生活が始まり生活環境も大きく変化する季節です。
慣れない土地での生活に対する不安や緊張感、人間関係の変化。環境の変化は人にとって大きなストレスの元凶となります。
そういった環境の変化による疲れや精神的なストレスが自律神経のバランスを乱し、春バテの症状を引き起こすおそれがあるのです。
春バテの対処法
- 1日3食、バランスの良い食事を
栄養バランスの良い食事を1日3食しっかりと摂りましょう。
偏った食事は春バテの原因のひとつでもあります。 - 質の良い睡眠
寝る前の飲食やスマホ・PCの操作を避け、リラックスできる環境にしましょう。
質の良い睡眠には疲労回復効果が期待できます。
就寝前に目の周りや首を温めるのも効果的です。 - 朝食はしっかり食べる
体内時計が乱れると自律神経も乱れてしまいます。
朝食をしっかり食べることで腸が刺激され、体内時計が整い、自律神経を整えるのにも役立ちます。
- 冷え対策をする
朝晩と日中との寒暖差が大きい季節。
体温調節ができるようにカーディガンやストールを着用したり、カイロ・温熱シートを利用して首や腰、お腹を温めるのもおすすめです。
- 適度な運動
体を動かすことで、血流の改善や代謝を上げ冷え防止効果が期待できます。
また、ストレス解消にもなるでしょう。
運動は自律神経のバランスを整えるのに非常に役立ちます。
無理をせず自分にできることから取り組んでいきましょう。
自律神経を整え、過ごしやすい毎日を

自律神経は交感神経と副交感神経で成り立っています。
交感神経は体を活発的に動かすときに働き、副交感神経は体を休めるときに働きます。
自律神経はこれらが交互に切り替わることでバランスを保っています。
しかし、過剰なストレスや生活習慣の乱れによって、交感神経と副交感神経との切り替わりがうまくいかず、自律神経に乱れが生じてしまいます。
春は生活環境の変化や寒暖差、気圧の変化など、心身の疲労が溜まりやすかったり、ストレスを受けやすい季節のため体調を崩しやすくなります。
生活習慣を整え、適度にストレスを発散することで、季節の変わり目に起こる不調を軽減することができるでしょう。


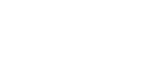 健康コラム一覧へ戻る
健康コラム一覧へ戻る