管理栄養士が分かりやすく解説【糖尿病の食事療法】これだけ抑えて!!
【大阪/梅田】大阪駅前の総合内科クリニック|西梅田シティクリニックがお届けする健康情報。
是非、みなさまの健康管理にお役立てください。

糖尿病学会が発表するガイドラインでは
「糖尿病の管理には、食事療法を中心とする生活習慣の是正が有効である」(合意率100%)
さらに
「食事療法の実践にあたって、管理栄養士の指導が有効である」(合意率95%)
と宣言しています。
日本では戦後の食の欧米化によって、Ⅱ型糖尿病患者が大きく増えました。
糖尿病の予防、進行抑制には、まずは肥満の解消が有効な手段であることには間違いありません。
適正体重を知る
そこで、自分が適正体重なのか、チェックしてみましょう。
適正体重のチェックには、BMIを算出してみることがおすすめです!
体重(kg) ÷ 身長(m) ÷ 身長(m) = BMI
例)身長165cm、体重60kgの人の場合
60(kg) ÷ 1.65(m) ÷ 1.65(m) = 22.0385…
⇒BMIは22.0と算出できます
肥満の解消には 1日のエネルギー量(カロリー) を適正にすることが欠かせません。
厚生労働省が発表しているBMIの目標値は下の表1のようになります。
表1 年齢別 目標BMI
| 年齢(歳) | 目標とするBMI(kg/m2) |
|---|---|
| 18~49 | 18.5 ~ 24.9 |
| 50~64 | 20.0 ~ 24.9 |
| 65~74 | 21.5 ~ 24.9 |
| 75以上 | 21.5 ~ 24.9 |
いかがでしょうか?目標値の範囲内に入っていますか?
入っていない場合にはこの範囲内を目指しましょう。
では、目標のだいたい中央値となるBMI22は何kgになるか計算方法をお伝えしますね。
例)身長158cmの方の場合
1.58(m) × 1.58(m) × 22 = 54.920…(kg)
⇒目標体重は約55kgと算出できます
適正エネルギー量を知る
エネルギー出納
飲食物から摂取したエネルギーは、生命機能の維持や、身体活動に利用され消費されます。
摂取と消費のエネルギー出納のバランスによって体重が増減します。
消費エネルギー < 摂取エネルギー ⇒ 体重が増える
消費エネルギー > 摂取エネルギー ⇒ 体重が減る
消費エネルギーには、性別、年齢、身長、体重、身体活動量に加え、基礎代謝量が大きく関係します。
基礎代謝量は、その人が生命を維持するのに最低限のエネルギー、つまり何もしなくても消費するエネルギーと言っても良いでしょう。
これは、筋肉量や体脂肪率など、身体の組成も関係してきます。
では、あなたに必要なエネルギー量(推定エネルギー量必要量)を算出してみましょう。
推定エネルギー必要量(Kcal) = 目標体重(kg) × 身体活動レベル(表2)
表2 身体活動によるエネルギー係数
| 身体活動量 | 具体例 | エネルギー係数ーテキスト |
|---|---|---|
| 軽い労作 | 大部分が座位の静的活動 | 25~30 Kcal/kg |
| 普通の労作 | 座位中心だが、通勤・家事・軽い運動を含む | 30~35 Kcal/kg |
| 重い労作 | 力仕事、活発な運動習慣がある | 35~ Kcal/kg |
例)目標体重60kg、身体活動量②普通の労作の人
60(kg) × 30~35( Kcal/kg) = 1800~2100(Kcal)
⇒1日に1800~2100Kcalが必要
ただし、理論上で算出された適正エネルギーはあくまで“目安”と考え、そのエネルギー量が本当にあなたの身体に合っているのかは実際にやってみないと分かりません。
病態や体重の経過を踏まえて適宜変更する必要があり、医師や管理栄養士など専門家に相談することをおすすめします。
食事療法の基本
糖尿病の食事療法は常に世界中で研究されており、様々な結果が発表されています。
近年はエネルギー制限よりも炭水化物の制限が主流となっていますが、炭水化物を制限することによって摂取エネルギーが減るので、エネルギー制限が糖尿病治療に無関係という明確な根拠はありません。
一方で、低炭水化物食によってHbA1cは改善傾向がみられたが体重減少はみられなかったという研究結果もあります。
つまり肥満と糖尿病の両方を改善するには、エネルギーも炭水化物量もコントロールすることについては効果が期待できる余地が十分にあります。
規則的に3食を摂りましょう
朝食を抜いたり、就寝前に間食したりすることで、肥満だけでなく、2型糖尿病の発症リスクを高めたり、血糖コントロールを安定したりするリスクが高まります。
食べ方を意識してみましょう
食べる順番や、咀嚼回数が血糖コントロールに影響を与えうることが注目されています。
- 食物繊維に富んだ野菜を先に食べる事で食後血糖値の上昇を抑え、HbA1cの低下や体重減少につなげられる
- タンパク質などの主菜を先に摂取してから主食の炭水化物を食べると食後の血糖値上昇は抑えられる
- 50歳以上から高齢の方に関しては、嚙む力が低下することで血糖コントロールを乱す可能性があり、先に食物繊維の多い野菜をよく噛んで食べ、主食を食べる事で食後高血糖を抑えられる
果物、お菓子、ご飯の糖質は違うもの!
果物に含まれる「果糖」という糖類は一定量までは糖尿病に影響を与えないと言われており、1日100gまでを目安にしましょう。
バナナ1本、りんご1/2個、みかん2個分くらいが100gです。
一方で、果物ジュースは糖尿病発症リスクを高めたという研究報告があり、生の果物とジュースは別のものだと認識すると良いでしょう。
ご飯と甘い飲み物やお菓子には糖類が含まれますが、ご飯は「ブドウ糖」という糖類であるのに対し、甘い物に使われる砂糖には「ショ糖」という種類の糖類が含まれます。
ブドウ糖はエネルギーとして使われやすいですが、ショ糖は血糖コントロールの悪化やメタボリックシンドロームを招くと言われています。
カロリーコントロールのために、お菓子を食べてご飯を抜く方もいらっしゃいますが、カロリーは同じでも、身体への影響は違うことを知っておきましょうね。
いかがでしたか?
糖尿病の治療には経過観察をして細やかに軌道修正をしていくことがとても大切です。
体質や病気の状態によってもお薬や食事の調整が必要になってくるので、専門の医療機関を受診して治療をおすすめします。
参考資料
- 動脈硬化性疾患予防ガイドライン2012年版
- 糖尿病診療ガイドライン2019
- 日本人の摂取基準 2020年版


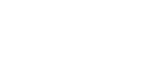 健康コラム一覧へ戻る
健康コラム一覧へ戻る